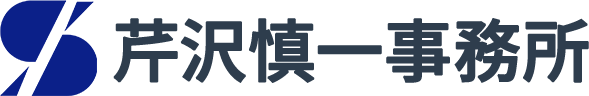こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
投資信託を選ぶとき、多くの人が「過去のリターン」や「人気ランキング」に目を向けがちです。しかし、長期運用を前提にするなら、リターンを大きく左右するのは“コスト”です。今日は、投資信託のコスト構造について整理してみましょう。
投資信託の代表的なコスト
投資信託にかかるコストは、大きく3種類に分けられます。
- 購入時手数料(販売手数料)
投資信託を購入するときに証券会社などに支払う手数料。最近は「ノーロード(無料)」のものも増えています。 - 信託報酬(運用管理費用)
運用中ずっとかかるコストで、信託財産から毎日差し引かれます。インデックス型で0.1〜0.3%台、アクティブ型で1%前後が一般的です。 - 信託財産留保額
解約時にかかる場合があるコストで、ファンドによって設定の有無が異なります。
見落とされがちな「隠れコスト」
実は、投資信託には目に見えるコスト以外にも「隠れコスト」と呼ばれるものがあります。
- 売買委託手数料(ファンドが株や債券を売買するときに発生)
- 有価証券取引税
- その他の事務管理費用
これらは「運用報告書」や「交付目論見書」に記載されていますが、普段はあまり意識されません。信託報酬が安いからと安心しても、実質コストを確認しなければ本当のコスト負担は見えないのです。
コストが与える長期的な影響
仮に年間の信託報酬が 1.0%と0.2%の投資信託で30年間運用した場合、最終的な資産額に数百万円単位の差がつくこともあります。コストは「毎年少しずつ資産を削る存在」であり、長期になるほど複利効果を大きく阻害します。
最後に
投資信託を選ぶ際に注目すべきは、
- 信託報酬はどの程度か
- 隠れコストも含めた“実質コスト”を確認したか
- 長期運用に適した低コスト商品か
というポイントです。投資成果は市場に左右されますが、コストを抑えるかどうかは投資家自身の選択次第。だからこそ、まず「コスト構造を理解すること」が投資家にできる最初の防衛策なのです。
今日も、あなたの資産形成がより賢く進むことを願っています。それではまたお会いしましょう!