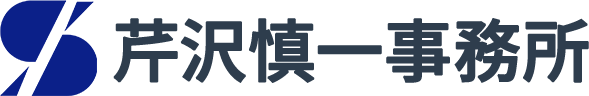こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
投資を考えるときによく出てくる言葉のひとつに「ボラティリティ(価格変動の大きさ)」があります。
株式市場は上下の振れ幅が大きい資産であり、その特性を理解しないまま投資すると、不安や失敗につながりやすくなります。
今日は「株式のボラティリティがポートフォリオにどんな影響を与えるのか」について整理してみましょう。
株式のボラティリティとは?
株価は経済状況や企業業績、金利動向、投資家心理など、多様な要因で日々変動します。
この変動幅を「ボラティリティ」と呼びます。
- 高ボラティリティ資産:株式、新興国株、暗号資産など
- 低ボラティリティ資産:国債、定期預金など
株式は高いリターンを狙える一方で、短期的には大きな値動きに晒されやすいのが特徴です。
ポートフォリオへの影響
① 短期的な資産価値の変動が大きくなる
株式比率を高くすると、ポートフォリオ全体の上下動が激しくなります。
含み益に浮かれたり、含み損に不安を感じたりしやすいため、心理的な影響も大きくなります。
② 長期的なリターンを押し上げる可能性
一方で、株式は長期的に見れば成長を続ける資産です。
時間を味方にすることで、短期のボラティリティを乗り越え、高いリターンを享受できるのも事実です。
③ 分散投資で緩和できる
債券や現金を組み合わせることで、株式の変動リスクを吸収できます。
株式100%よりもリターンは下がりますが、安定性が増し、継続投資しやすくなります。
投資家が取るべき視点
- リスク許容度を把握する
「どれくらいの損失なら耐えられるか」を自分の生活と心理の両面で理解することが重要です。 - 資産配分を設計する
株式だけに頼らず、債券や現金を組み合わせ、ボラティリティを自分に合った水準に調整しましょう。 - 長期視点を忘れない
ボラティリティに振り回されて売買を繰り返すと、結果的にリターンを下げてしまうことがあります。
短期の値動きではなく、10年・20年先を見据えた投資が大切です。
ボラティリティは「敵」ではない
株式のボラティリティは、投資家にとって避けられない現実です。
しかし、それは「危険」ではなく「成長の裏返し」とも言えます。
大切なのは、変動を理解し、自分に合ったバランスで取り入れること。
最後に
ボラティリティを怖がりすぎると投資を避ける原因になりますし、無視しすぎると資産が不安定になります。
株式の特性を正しく理解して、長期的な資産形成に活かしていきましょう。
それでは、今日も最後までお読みいただきありがとうございました。
また次回のブログでお会いしましょう。