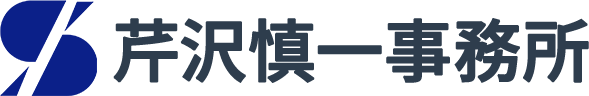こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
家計相談をしていると「保険を見直したいけれど、どれをやめてどれを残せばいいのか分からない」という声を本当に多く聞きます。
保険は「安心」を買うものですが、知らないうちに“余計な安心料”を払い続けていることも少なくありません。
今日は、やめるべき保険と残すべき保険を見分けるシンプルな基準をお話しします。
保険の基本ルール「万一のリスク × 貯蓄でカバーできない額」
そもそも保険は“低確率だけれど大きなダメージになる出来事”に備えるものです。
たとえば、入院費の数万円程度なら貯蓄で対応できますが、働けなくなった場合の数千万円規模の損失は貯蓄だけでは難しい。
この“カバーできない額”を補うのが保険の役割です。
やめてもいい保険の特徴
- 貯蓄で十分カバーできるリスク(短期入院、通院など)
- 過剰な特約(がん、先進医療、災害など細かく分かれているもの)
- 貯蓄性重視の保険(学資保険や終身保険で利回りが低いもの)
特に「掛け捨てはもったいないから貯蓄型を選ぶ」という考え方は要注意です。
利率の低い商品を長期で抱えるより、自分で投資や積立をしたほうが効率的なケースが多いです。
残すべき保険の特徴
- 死亡保障(特に子どもが小さい家庭)
- 就業不能保険(働けなくなるリスクへの備え)
- 高額医療費に対応する医療保険(最低限でOK)
つまり、「一家の収入が止まると生活が成り立たないリスク」に対しては、まだ保険の役割が大きいといえます。
保険を“断捨離”するステップ
- 加入中の保険をすべて書き出す
- 「リスク × 貯蓄でカバーできるか?」を1つずつ当てはめる
- 不要なものは解約、必要なものは掛け捨てでシンプルに残す
こうして仕分けをすると、毎月1〜2万円の固定費が浮くこともあります。
最後に
保険は「安心料」ですが、過剰に入りすぎると「家計の足かせ」にもなります。
やめる保険・残す保険を見極めることで、本当に必要なところにだけお金を集中させることができます。
お金の安心は“保険”だけではなく、“貯蓄や投資”とバランスを取ってこそ。
その視点を忘れずに、今日から保険証券を一度見直してみてください。
お金は数字ではなく、あなたの人生を支える道具です。その視点を忘れずに。ではまた!