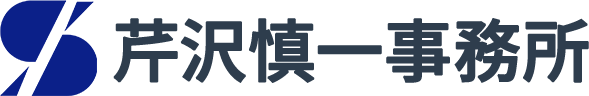こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
わが家では、子どもの教育資金づくりの一環としてジュニアNISAを活用してきました。非課税で投資ができる制度は、家計にとってとてもありがたい存在でした。
しかしご存じの通り、ジュニアNISAは2023年で新規投資の受付が終了。わが家でも「これからどうする?」という大きなテーマに向き合うことになったのです。
終了後に感じた“空白感”
それまで毎月コツコツ積み立てていた仕組みが終わると、不思議とぽっかりとした空白が生まれました。
「せっかく投資に回していたお金を、そのまま生活費に流してしまっていいのか?」
「子どものために続けていたのだから、次の枠をどうにか考えたい」
そんな気持ちから、次の一手を真剣に検討することになりました。
わが家の選択肢は2つだった
話し合いの中で出てきたのは、大きく2つの方向性です。
1つ目は、親である私や妻の新NISA枠を使って、子どもの教育資金用として積み立てていく方法。
2つ目は、学資保険や定期預金など、より安全性を重視する形で移す方法。
どちらにもメリット・デメリットがありましたが、私たちが選んだのは 「新NISAを活用する」 という道でした。
“目的の明確化”が決め手
なぜ新NISAにしたのか。
それは「教育資金はまだ10年以上先に使うお金だから、成長の余地を活かしたい」と考えたからです。
もちろんリスクはありますが、長期で見れば分散投資のメリットが働きやすい。ジュニアNISAで続けてきた流れを、そのまま大人の制度に引き継ぐことができるのも安心材料でした。
一方で「万一、急にお金が必要になったときに困らないように」というリスク対策として、預貯金も並行して積み立てる仕組みにしています。
最後に
ジュニアNISA終了後の選択肢は家庭ごとに異なります。
投資を続けるのも、預金に回すのも、どちらが正しいというわけではありません。大切なのは「目的」と「リスク許容度」を照らし合わせること。
わが家の場合は、新NISAを教育資金の“次の器”として選びました。
制度は変わっても、「子どもの未来に備える」という目的がぶれなければ、きっと安心して続けられるはず。
今日の話が、同じように悩んでいる方のヒントになれば嬉しく思います。