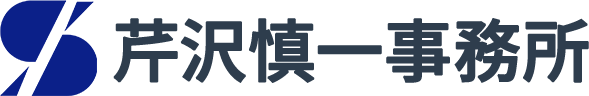こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
今日は、私が地方都市の食品メーカーで手がけた与信管理改革のお話をしましょう。
「大口取引先に頼りすぎるとどうなるか」――現場で直面したリアルな教訓です。
きっかけは“売上の9割を占める顧客”
依頼をくださったのは、地元で40年以上続く冷凍食品メーカー。
堅実な経営を続けてきたのですが、社長の口から出たのは意外な一言でした。
「最近、メインのお得意先の支払いが妙に遅れててね…。ちょっと不安なんですよ」
詳しく調べてみると、その顧客は全国チェーンの大手スーパー。
売上の9割以上を占める超・大口取引先でした。
しかし、そのスーパー本体の業績はここ数年下降線。遅れ気味の支払いが危険信号のサインだったのです。
初日の現場調査
会社の帳簿を開き、私は社長にこう尋ねました。
「もしこのスーパーからの入金が止まったら、会社は何か月持ちますか?」
社長は数秒黙り込み、苦笑いを浮かべました。
「…正直、1か月もたないでしょうね」
“売上はあるのに、現金が残らない”。
これは典型的な与信リスクの集中依存型でした。
改善プラン──「分散と見える化」
私は3つの方針を打ち出しました。
- 売上依存度の分散
既存の大口顧客への依存を徐々に下げ、中小規模の新規取引先を増やす。 - 与信ルールの再構築
大口であっても必ず信用調査を行い、決算内容や財務体質を定期的にチェック。 - キャッシュフローの見える化
資金繰り表を週次で更新。入金遅れが発生したら即座にアラートを上げる仕組みに。
営業現場での抵抗
営業担当者からは当然こんな声が上がりました。
「そんなこと言っても、新しい取引先を探すのは大変ですよ」
私は穏やかに答えました。
「“今の売上”を守るのは大事です。でも、“未来の安定”を守るのはもっと大事です」
数字の裏にあるリスクを伝えると、少しずつ現場も動き始めました。
半年後の成果
6か月後には、売上構成が変化。
大口スーパーへの依存度は9割から7割へ低下。
さらに、取引先を分散させたことでキャッシュフローが安定し、社長もこう語ってくれました。
「夜中に資金繰りの心配で目が覚めることが減りましたよ」
最後に
この案件からの学びはシンプルです。
- 大口取引先だから安全、は幻想
- 信用は“相手の規模”ではなく、“数字と仕組み”で確認するもの
- 与信管理は攻めの営業活動を守る“盾”
信用を守る仕組みを整えることが、会社の未来を守る最強の戦略です。
#慎一のマネー講座 では、こうした与信や資金繰りのリアルな現場から学べる話を続けて紹介していきます。
「うちも似ているかも」と感じたら、それは改革のチャンスかもしれません。