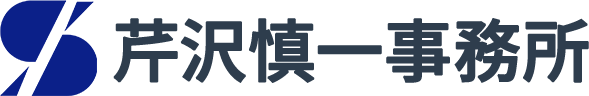こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
2023年10月から始まったインボイス制度(適格請求書等保存方式)。
導入前は「うちは関係ない」と思っていた企業も、いざ始まってみると請求書の書式や取引条件の見直しに追われています。
今日は、私が支援した サービス業B社 の事例を交えながら、中小企業が制度の波に溺れずに対応するためのポイントをご紹介します。
導入直後の混乱
B社は地方都市でイベント企画運営を行う従業員20名の会社。
制度開始直後、取引先の一部からこんな連絡が立て続けに入りました。
- 「インボイス番号が記載されていない請求書は受け取れない」
- 「課税事業者でない場合、消費税分を減額する」
B社は免税事業者との取引も多く、請求書フォーマットも統一されていませんでした。
結果、月末の請求処理が普段の2倍の作業時間に。
インボイス制度対応の実務ポイント
1. 登録事業者かどうかの確認
まず、自社が適格請求書発行事業者に登録しているかを確認。
登録していない場合、取引先の仕入税額控除に影響するため、取引条件の再交渉が必要です。
2. 請求書フォーマットの統一
制度に対応するための最低限の記載項目は以下の通り
- 適格請求書発行事業者の登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象は明示)
- 税率ごとの対価の額(税抜きまたは税込)
- 消費税額
- 請求元の名称
クラウド会計ソフト(freee、マネーフォワード等)を活用すれば自動対応可能です。
3. 取引先の属性管理
免税事業者か、課税事業者か、登録番号はあるか——これらを一覧化。
B社ではExcelで「インボイス取引先台帳」を作成し、経理と営業が随時更新する仕組みを導入しました。
B社が得た効果
制度対応を整理した結果、B社では次のメリットが生まれました。
- 請求業務の工数が制度開始前の水準に戻る
- 取引先との条件交渉がスムーズになり、消費税分の減額リスクを回避
- 経理担当の属人化解消(誰でも同じ手順で請求書発行可能に)
まとめ
インボイス制度は、一見すると“事務負担が増えるだけ”に見えます。
しかし、制度対応の過程で請求・支払の流れを見直せば、業務効率化と取引条件の明確化という副産物が得られます。
制度の波は避けられません。
ならば、泳ぎ方を覚え、むしろ波を利用して進む。
それが、中小企業の生き残る道です。
ではまた次回。 #慎一のマネー講座 でもお会いしましょう!