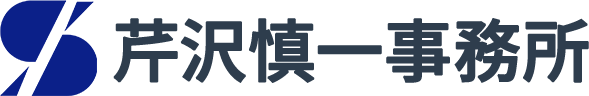こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
今日は、少し旅の話を交えた金融コンサルの事例をご紹介します。
舞台は南国の都市国家・シンガポール。
私が現地の日系企業の「与信管理体制づくり」をお手伝いしたときのことです。
到着早々、浴びた“南国の洗礼”
シンガポールに降り立ったのは、湿度90%を超える蒸し暑い午後。
「スーツ着てきた自分を誰か止めてくれ」と心の中でつぶやきながら、現地オフィスへ向かいました。
クライアントは、東南アジアで急成長している日系の部品商社。
取引先は中小企業から大手まで幅広く、売掛金も数百万ドル単位。
ところが、現地スタッフに与信管理の経験がほとんどなく、
「取引先の支払遅延が増えてきた」という相談を受けたのです。
現地流の“信用”の危うさ
最初の打ち合わせで、経理担当者が自信満々にこう言いました。
「社長が“この会社は大丈夫”と言ったので、信用調査は不要です」
…いや、気持ちはわかります。
トップ同士の握手が重んじられる文化は確かにある。
しかし、それは“信用”ではなく“信頼”——
ビジネスの世界では、数字と記録が裏付ける信用こそが命綱です。
“信用のパスポート”を作る
そこで提案したのが、
①取引先の財務情報・支払履歴の可視化
②社内で統一した与信ランクの設定
③延滞発生時の対応マニュアル化
特に①では、日本では当たり前の「信用調査レポート」を現地語対応で導入。
さらに、過去2年分の入金履歴をグラフ化して、遅延傾向をひと目で確認できるようにしました。
この仕組みをスタッフに説明すると、
「これなら社長が出張中でも判断できますね!」と目を輝かせてくれました。
実は“文化”も管理項目
一方で、数字だけでは測れない要素もあります。
例えば、シンガポールでは旧正月前に資金繰りが厳しくなる企業が多い。
理由は、社員全員への“お年玉”が習慣として根付いているからです。
こうした商習慣を踏まえた支払スケジュール調整も、与信管理の大事な仕事。
つまり、数字と文化、その両方を理解してこそ、真の“信用”が築けます。
成果とその後
半年後、クライアントの延滞率は30%以上減少。
現地スタッフが自ら新規取引先の与信評価を行い、社長も「これで安心して営業できる」と喜んでくれました。
最後に
“信用”とは、異国では言葉よりも強いパスポートです。
国や文化が違っても、「約束を守る仕組み」は普遍のルール。
皆さんのビジネスや日常生活にも、ちょっとした「信用の見える化」を取り入れてみてください。
それでは、また次回お会いしましょう!