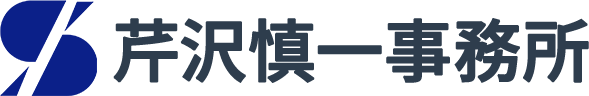こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
今日は少しスーツケースの匂いがする話をしましょう。
数年前、私はシンガポールとオーストラリアに駐在し、日系企業の「海外取引の信用調査」や「与信管理体制づくり」を支援していました。
「海外の取引先って、どうやって信用度を判断すればいいんですか?」
これは現地で一番よく聞かれた質問です。
日本国内なら、信用調査会社のレポートや商業登記簿、取引履歴からある程度判断できますが、海外ではそうはいきません。国によってルールも文化も、商習慣もバラバラです。
文化の違いは与信リスクの違い
ある日、シンガポールの中堅メーカーと契約を進めていた日系企業から相談を受けました。
条件は悪くない。財務資料も、こちらの要請に応じて出してくれた。
ところが…提出された決算書、妙に“きれい”なんです。利益が毎年同じくらい、負債も微動だにしない。
現地の会計士に聞くと、笑いながら一言。
「この国では、税務上の理由で数字を丸めるのは珍しくないよ」
つまり、数字は「正しい」かもしれないけれど、「そのまま信じていい」とは限らない。
この瞬間、私は痛感しました。海外与信管理は数字だけでは完結しない、と。
現地ネットワークは命綱
そこで役立つのが、現地ネットワークです。商工会、業界団体、そして同業他社。
「この会社、支払いは早いけど、在庫回転が遅いよ」
「社長は信用できるけど、経営は奥さんが握っているから要注意」
…そんな“数字に出ない情報”が、現地の信用判断では金よりも価値を持つことがあります。
私は毎週のようにローカルのビジネス交流会に顔を出し、雑談半分の情報交換を繰り返しました。
こうして集まった“生の声”は、財務諸表よりもよく、企業の実像を教えてくれます。
システム+人間の目=最強
結局、最終的にたどり着いたのは「システムと人間の目の両立」でした。
オンラインの与信管理ツールで財務や取引履歴をスクリーニングし、
現地担当者や私自身の足で稼いだ情報で裏を取る。
一方だけでは偏る。両方あって初めて、バランスの取れた判断ができます。
最後に
海外ビジネスは、海の向こうに“未知の魅力”と“見えないリスク”が同居しています。
でも、だからこそ、慎重さと柔軟さの両方を持った与信管理が欠かせません。
帰国前夜、シンガポールの海沿いのカフェで現地スタッフと語り合った時、
「あなたのおかげで安心して契約できるようになった」と言われました。
波の音と一緒に、その言葉が胸に沁みたのを今も覚えています。
海外の海は広い。でも、確かな羅針盤さえあれば、迷わず進めるものです。
ここまで読んでくださりありがとうございます。興味を持った方は #慎一のマネー講座 のSNSもぜひご覧ください!