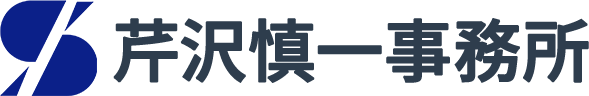こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
普段は日本各地の自治体や企業で「お金の使い方」や「金融サービスとの正しい付き合い方」をお話ししている私ですが、今日は少し毛色の違うエピソードを。
舞台は南半球、カンガルーとコアラと…そしてなぜか与信管理の議論が飛び交う会議室、オーストラリアです。
きっかけは一本のメールから
数年前、ある日系小売企業の担当者からこんな相談が届きました。
「オーストラリアの現地法人でBNPL(後払い)サービスを導入したいんですが…与信の考え方が日本と全く違って、正直お手上げでして。」
ええ、予想はしていましたが、聞けば聞くほどカルチャーショックの連続。
日本では「年収」 「勤続年数」 「過去の延滞履歴」といった“返せる能力”のチェックが主流。
一方オーストラリアは「生活費」 「支出習慣」 「他社の分割契約状況」までしっかり覗き込みます。
つまり、返せるかどうかだけじゃなく「借りるべきかどうか」まで審査する文化なんですね。
文化の違いはまず“見える化”から
初回の打ち合わせで私がしたことは、日豪の与信文化を図解に落とし込むこと。
難しい金融用語は封印し、「誰でも分かる言葉」で並べて比較します。
- 日本:年収は? 勤続年数は? 延滞歴は?
- 豪州:月の生活費は? Uber Eatsにいくら使う? 分割払いは何件?
会議室が一瞬ざわめき、「そりゃ発想が全然違いますね」という声が上がりました。
ここで経営陣が腹落ちしないと、その後の制度設計が机上の空論で終わりますから。
ロジック再設計はまるで文化翻訳
次は審査ロジックの構築です。
現地のフィンテック企業と連日リモート会議を重ね、日本の「返済能力重視」に、豪州流「利用習慣リスク評価」をどう組み込むかを議論しました。
最終案は三段構え。
- AIによる事前スコアリング(生活パターンも評価)
- 初回限度額の抑制(いきなりフル枠は与えない)
- 利用履歴に応じた段階的限度額アップ
特に3つ目の「信頼を積み上げる方式」は、日本の「初回からフルオープン型」とは正反対。文化の折衷案でした。
半年後、現場からの報告
導入から半年、現地法人の担当者から嬉しい報告が届きました。
「不払いトラブルが減って、顧客との距離が近くなった気がします」
「払えるけど、あえて借りない人も出てきました」
そう、それこそが狙いだったんです。
金融は数字の世界に見えて、実は“人の選択”がすべて。文化に合わせた設計は、その選択を健全な方向に導きます。
国境を越えるには“翻訳力”がいる
今回の経験で再確認したのは、「金融の常識は国境で変わる」という当たり前でありながら厄介な真実。
日本での当たり前が、海外では不思議がられ、時に疑問視される。
だからこそ必要なのは、制度や数値の単なる翻訳ではなく、“文化そのもの”を翻訳する力。
それさえあれば、どんな市場でもBNPLだろうと与信管理だろうと、しっかり根を下ろせる仕組みが作れる。
いかがでしたか?興味のある方は #慎一のマネー講座 をぜひチェックしてください!
それではまた次回お会いしましょう!