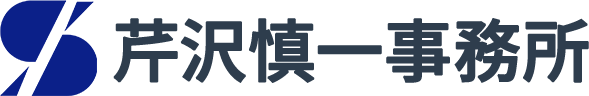こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
今日は、私が先日とある自治体で行った「安心・安全な金融サービスの選び方」セミナーの様子をご紹介します。
テーマは、最近身近になった「後払いサービス」との付き合い方です。
会場の雰囲気は、まるで町内会の寄り合い
会場は、市の文化センター。平日午後にも関わらず、50名以上の市民の方が集まってくださいました。
60代前後の方が多いですが、仕事の合間に来られた30代・40代の方もちらほら。
冒頭、私はこんな質問を投げかけました。
「皆さん、スマホで買い物をしたことはありますか?」
ほとんどの手が上がります。
続けて聞きました。
「その中で、“後払い”を選んだことがある方は?」
半分くらいの手が上がりました。
それくらい、この仕組みはすでに生活に入り込んでいるんです。
後払いって何が危ないの?
後払いは便利ですが、「お金を払う日が後になる」という一点で、使い方を間違えると家計が一気に苦しくなることがあります。
セミナーでは、こんな図を使って説明しました。
- 今日:買い物をしてもお金はまだ払わない
- 後日:請求書やアプリ通知でまとめて支払い
- もし延滞すると:手数料や利息が加算
参加者の方からは、
「えっ、手数料ってそんなに高いの?」
「延滞したらすぐ信用情報に傷がつくんですね…」
という驚きの声が上がりました。
安全に使うための“3つのマイルール”
セミナー後半では、「明日からすぐできる安全対策」として、次の3つを提案しました。
- 利用は月1回までにする
- 必ず支払日をカレンダーに書き込む
- 生活費の中から払える範囲だけ利用する
これらは専門的な家計管理ではなく、生活習慣として取り入れられるものです。
数字に強くない方でも、無理なく実践できます。
その後の反響
翌週、市役所の担当者から「参加者の方が家族で“お金の使い方ミーティング”を開いたそうです」という報告をいただきました。
中には「孫にもスマホ決済の危険性を説明してあげた」という方も。
金融の知識は、世代を超えて役に立つんです。
最後に
お金の使い方は、日常生活のちょっとした習慣で大きく変わります。
便利なサービスも、正しく知れば強い味方に。
逆に、知らないまま使うとあっという間に敵になってしまうこともあります。
皆さんもぜひ、「便利さの裏側」にも目を向けてみてくださいね。
次回は、高校生向けに行った「はじめてのクレジットカード講座」の様子をお届けします。
それでは、 #慎一のマネー講座 でまたお会いしましょう!