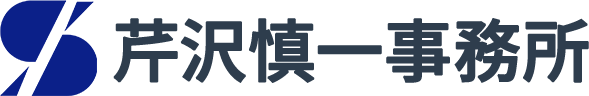こんにちは。
マネーリテラシー講師の芹沢慎一です。
普段は日本全国を飛び回りながら、金融セミナーやリスク啓発講座を担当していますが、今回はちょっと視点を変えて、私がかつて携わった「海外金融コンサル案件」のお話をしてみようと思います。
舞台は、南半球の陽気な大陸 オーストラリア。
カンガルーとコアラのイメージしかなかった私が、まさか現地のフィンテック企業と与信管理制度について真剣なディスカッションを交わすことになるとは、数年前の私は夢にも思わなかったでしょう。
事例 日系企業×豪州スタートアップの「与信管理」再構築
きっかけは、ある日系小売企業からの相談でした。
「オーストラリア現地法人で、BNPL(後払い)サービスを導入したいんだけど、与信審査のルールが全然日本と違って困ってるんですよね……」と。
ええ、そうなんです。
日本の与信文化は、どちらかというと「信用情報」 「属性データ」 「支払履歴」に重点を置きますよね?
一方、オーストラリアでは、「クレジットスコア」に加えて、生活費や支出習慣まで見られるのがスタンダード。
要するに、“この人は返せる人”ではなく、“この人は本当に借りるべきか”を見極めようとする傾向が強いんですね。
コンサルのポイント① 日豪の“金融文化ギャップ”を可視化する
まず私が行ったのは、日本とオーストラリアの与信基準の違いを「図解」して経営陣に伝えることでした。
難しいことを難しく伝えては意味がない。私のモットーは「専門用語を使わずに、誰にでもわかる説明」ですから。
たとえばこんな感じです
日本 「年収は?勤続年数は?」 「過去に延滞は?」 「どの銀行と付き合ってる?」
オーストラリア 「月々の生活費はいくら?」 「Uber Eatsにいくら使ってる?」 「分割払いの契約は?」
この違い、なかなかインパクト大です。
コンサルのポイント② リスク許容度を“文化として”再設計する
次に着手したのが、審査ロジックの再構築です。
日本的な「返済能力重視」の視点に加え、豪州の「利用習慣リスク」の要素をどう組み込むか?これが最大のチャレンジでした。
現地のスタートアップ企業と何度もディスカッションを重ね、最終的には
AIスコアリングによる事前評価
初回限度額の制限(慎重なスタート)
利用履歴に応じた段階的な信頼構築
…という三段構えの与信管理体制を構築。
特に“段階的な信頼”というアプローチは、日本の「初回からフルオープン型」与信文化とは真逆。まさに文化の折衷案でした。
その後の話 数字より、信用を積むことの大切さ
この仕組みを導入して半年後、現地法人の担当者から連絡がありました。
「トラブルは激減し、顧客との信頼関係が深まった感覚があります」
「“払えるけど借りない”選択をする人が増えてきました」
そうそう、それが聞きたかったんです。
結局、お金の管理って、数字の話じゃなく“人の選択”の話なんですよね。
最後に 国が違えば「正しさ」も変わる
今回のケースを通じて改めて感じたのは、金融における「常識」なんて国によってまったく違うということ。
私たち日本人が当たり前と思っていることも、海外では「あれ?なんでそんなこと気にするの?」と首をかしげられる。逆もまた然りです。
だからこそ、大切なのは「相手の文化を知り、自分たちの考え方を翻訳する力」なのかもしれませんね。
というわけで今回はこのへんで。
次回は、シンガポールで遭遇した「クレジットカード不要論」の現場からお届けする予定です。
それでは、 #慎一のマネー講座 でまたお会いしましょう!